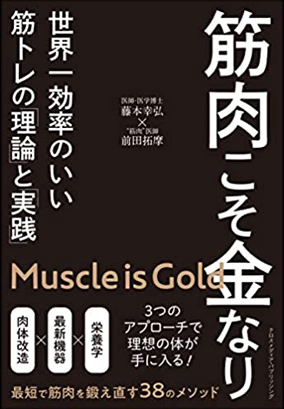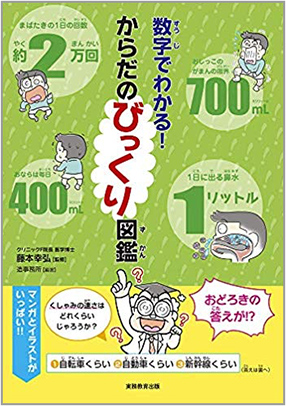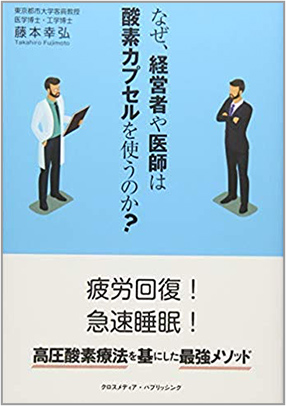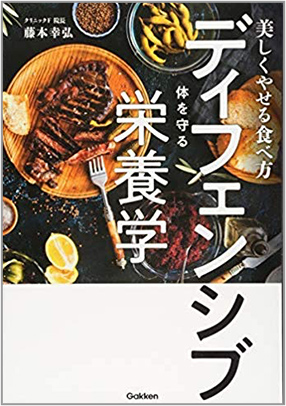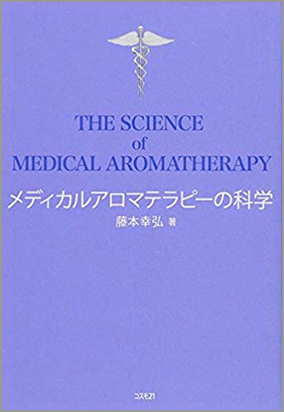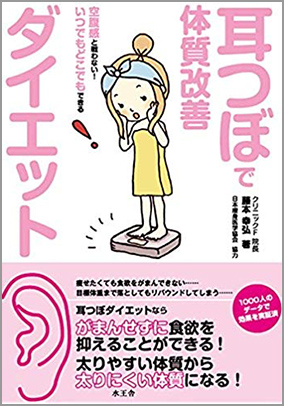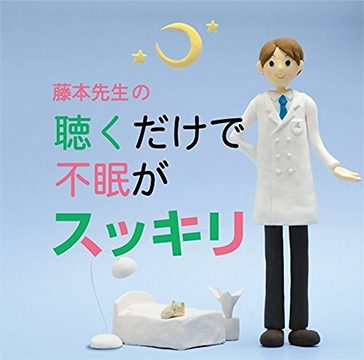明日発売のMAQUIAですが、小嶋陽菜さんの通っているクリニックとして、クリニックFをご紹介頂きました。
ありがとうございます。
本当に透明感のある美しい肌ですよね。




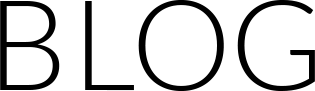 藤本幸弘オフィシャルブログ
藤本幸弘オフィシャルブログ
明日発売のMAQUIAですが、小嶋陽菜さんの通っているクリニックとして、クリニックFをご紹介頂きました。
ありがとうございます。
本当に透明感のある美しい肌ですよね。



今月号の欧州皮膚科学会専門誌。
ニキビ跡治療についてでしたが、レーザーやRFなどのエネルギーデバイスを使用した総論がありました。
皮膚科学会誌にしては珍しい特集。




米国レーザー医学会では、「すでにニキビ痕治療は完成した」と言われて早10年。
いまだに古い治療を保険診療でされているドクターも多いですが、世界の常識は日本の非常識。
世界の治療法は大きく変わってきています。
新紙幣が発行されましたね。
一万円札も
聖徳太子 → 福沢諭吉 → 渋沢栄一
と変化してきましたが、これは
国づくりと法整備 → 国民教育者 → 創業経営者に関わった人
ですので、今の時代に即した良い選択だったんじゃないかと思います。
***
貧しい農家に生まれた渋沢栄一は、明治維新にかけて海外修学した経験から攘夷論者の姿勢を一変させて、個人の利益よりも公益を重視し、国家全体の発展に寄与することを目指しました。
西洋の先進的な技術や制度を日本に導入し、多くの企業を設立しましたが、株を買い占めることなく、その企業を自身の支配下に置くことを避けました。
公益を重視する栄一は、自身の利益よりも国家全体の発展を優先したのです。
栄一は、設立した企業の株式を売却して得た資金を、新たな企業の設立のための原資として活用しました。
彼は企業の維持運営にはあまり興味を持たず、最低限の出資のみを行い、残りの資金は広く一般から出資を募る株式会社方式を採用しました。
GHQの財閥解体の時も、一旦は渋沢財閥も15財閥の一つと判断されるも、再調査の結果、その規模と株式所有企業への支配力の点からも渋沢同族株式会社は財閥の持株会社には相当せず、指定解除を願い出る様に通知されました。
彼の視野は広く、三井や三菱などの財閥系が学卒者を多く採用して自社のために人材を育成したのとは異なり、日本国家全体の底力を上げるための教育事業にも力を入れました。
明治維新以降の日本の飛躍的な発展の社会的なインフラの礎を築いた人物だったという事ですよね。

今日は東京都知事選挙開票日ですが、ここ何十年もの間、都知事が変わっても何ら変化がない状況が続いています。
日本は官僚が強いんでしょうね。
形骸的な公約とパフォーマンスの上手いトップが選挙で変わっても、結局日本は中身が変わらない。
100年後とは言わずとも、せめて30年後のおそらくサブカル化した東京に対して、伸び代のある政策をして欲しいですが、まあ革命でも起こらない限り、現状のシステムは変わらないんでしょうね。
ニュルブルクリンク。僕も昔、走りました。
アヴェンタドールとウラカン。
ストレートエンド300km超える速度でしたが、あのブラインドコースを6分切る車があるとは。
R32GTRやF355も今乗ってみると驚くほど遅いですよね。
人間の能力の開花というより、様々な運転サポートAIも付いたからでしょうね。

https://bestcarweb.jp/feature/column/902682



サンパウロの空港ラウンジにあった雑誌。