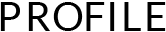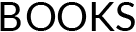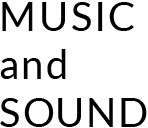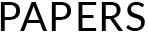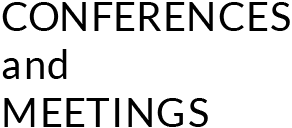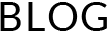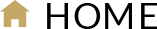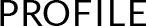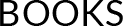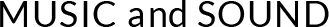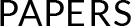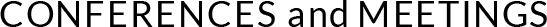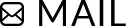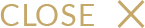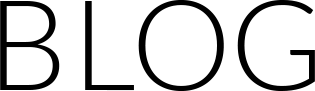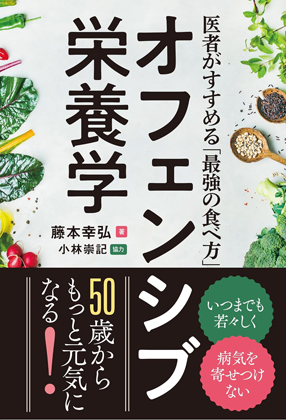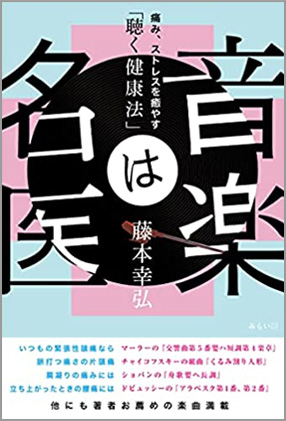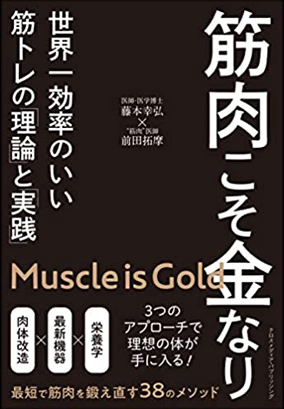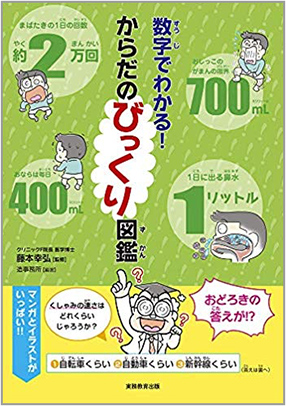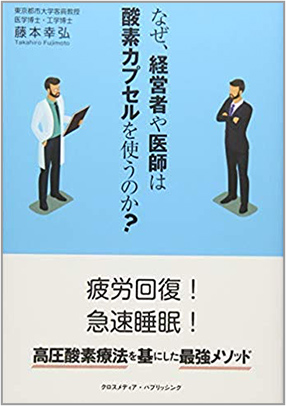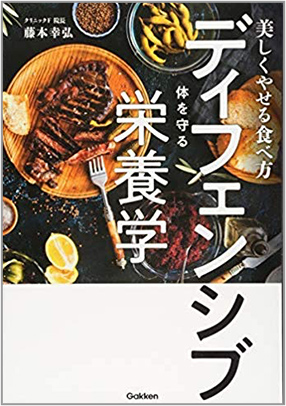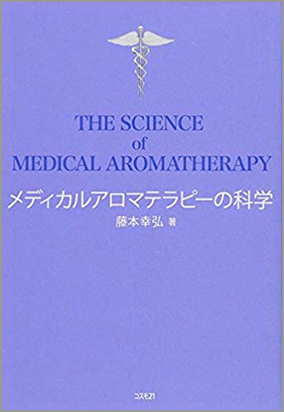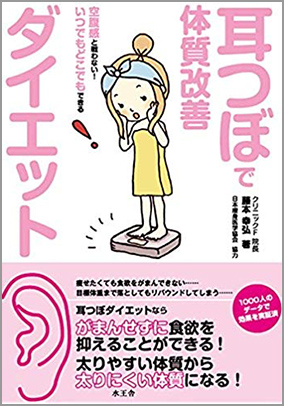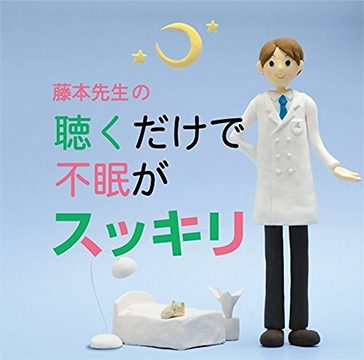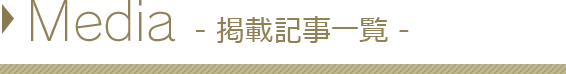Amarone della Valpolicella 大好きです。
9年前の今日ヴェローナで40€で買って飲んだSan Rusticoと、先日フランクフルトのトランジットで135€買ったMasi。
いつ飲むか思案中です。

アマローネが世間に知られるようになったのは1936年のこと。
さらにDOCGに昇格したのも2010年。
他のイタリア高級ワイン「バローロ」、「バルバレスコ」、「ブルネッロ」(これらは1980年に昇格)に比べると随分遅れてDOCGに昇格したのだそうです。
陰干しぶどうで作られた濃縮なちょっと苦い味が好きなんですよね。
いつ飲んでも何度か訪れたあのヴェローナの景色と野外オペラを思い出します。
現地で飲むワインは最高です。
また行きたい。