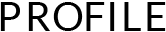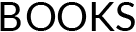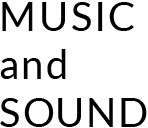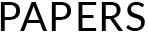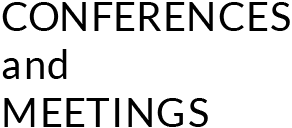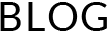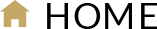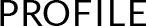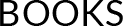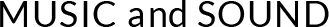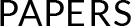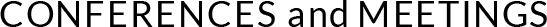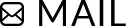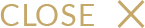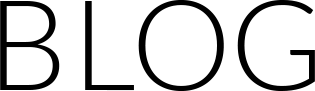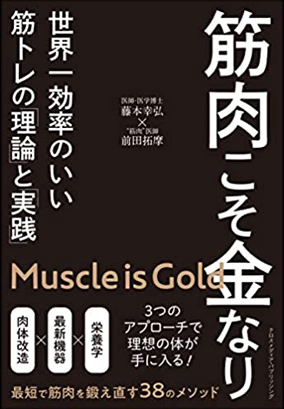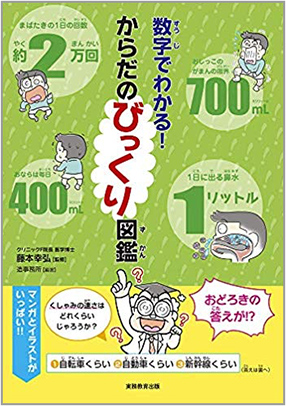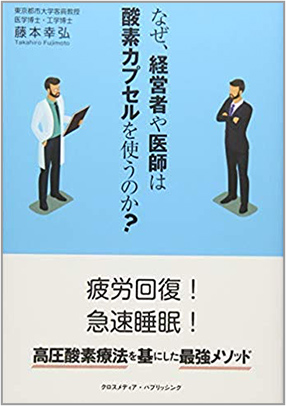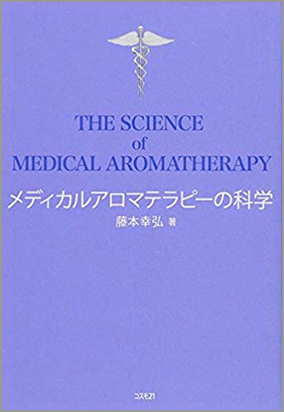本日はチェリスト金子鈴太郎さんをお招きしたゴルフ医科研にてチェロとワインの会。バッハ無伴奏組曲第4組曲でした。

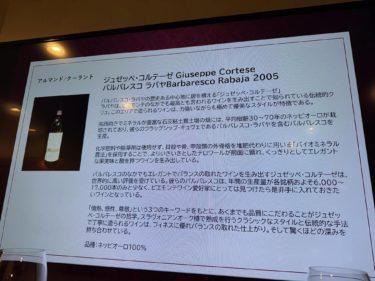

https://www.facebook.com/1486146253/videos/pcb.10236569212118712/1281701766242374
今回でチェロの組曲6番までの3週目。
何度も聴いていると、どんどん耳が肥えてきますが、今回、ヒントを得て、この組曲の数学的な解析を試みてみました。
考慮した要素は四つ
〇リズムの周期性と対称性(各組曲のプレリュードや舞曲の拍子やパターンの数学的解析)
〇旋律の幾何学的パターン(音程やフレーズの構造を幾何学的に分類)
〇調性の分布と数学的変換(調の遷移や音の頻度分布を統計的に解析)
〇フーリエ解析による周波数特性(フレーズごとのスペクトル分布を比較)
です。
バッハ無伴奏チェロ組曲の数学的分析
バッハの無伴奏チェロ組曲第1番から第6番までには、音楽的美しさの背後に様々な数理的特徴が潜んでいます。ここでは各組曲について、リズムの周期性と対称性、旋律の幾何学的パターン、調性の分布と数学的変換、フーリエ解析による周波数特性の観点から特徴と違いを考察します。
第1番 ト長調 (BWV 1007)
リズムの周期性と対称性: プレリュードは有名なアルペジオの連続で、16分音符が休みなく続く一定周期のパターンを持ち、安定した脈動を生み出します。各舞曲(アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット、ジーグ)は二部形式(AとB)で構成され、両部分がほぼ等しい長さになるという対称構造をとります(サラバンドでは典型的に各フレーズが4小節単位で対称的に構成されています)。この対称性により、聴き手には均整の取れたリズム感が伝わります。
旋律の幾何学的パターン: プレリュード冒頭では広い音域に渡る分散和音(例えば低い開放弦Gから高い音への跳躍)が用いられ、「広がりのある和音」による空間的な広がりを感じさせます。旋律線は主に分散和音と音階的な進行で構成され、音高が上下にゆるやかにアーチ状に動くパターンが多く、幾何学的にはなだらかな波形のようです。また各舞曲でも、アルマンドは流れるような階段状の動き、クーラントやジーグでは
機敏な跳躍が見られるなど、旋律の形状パターンに特徴があります。
調性の分布と数学的変換: 第1番は調性がト長調に安定しており、主音Gと属音Dを中心に音が配置されています(実際、チェロの開放弦GとDが調号に含まれるため共鳴が豊かです)。プレリュードでは和音分散により主和音から属和音へと進み、再び主調に戻るという典型的な調的巡回を示します。これは数学的に見ればトニックからドミナントへの遷移(調の変換)とその回帰であり、楽曲全体に明快な構造を与えています。また各舞曲内でもフレーズの反復進行(シーケンス)が用いられ、モチーフが一定の音程だけ移調されて繰り返されることで平行移動的な対称性を示しています。例えばメヌエットでは主題が異なる高さで再現され、これは音楽上の**数学的変換(移調)**と言えます。
フーリエ解析による周波数特性: 第1番プレリュードの音型はほぼ周期的であるため、時間信号としてフーリエ変換すると主要な周波数成分は拍子に対応する低周波数帯に集中するでしょう。一方、音価が短い16分音符が連続するため、高い反復周波数成分も現れます。全体としては滑らかな1/fスペクトル(低周波ほど強い強度)に近いと考えられ、実際音楽のリズムスペクトルは1/f法則に従うとの研究報告もあります。この1/fゆらぎ的な周波数特性は、曲に秩序とランダム性の両面(予測可能性と意外性)のバランスが取れていることを示唆し、バッハ音楽の自己相似的な構造にも通じています。
第2番 ニ短調 (BWV 1008)
リズムの周期性と対称性: ニ短調の第2番では、プレリュードが第1番とは対照的に緊張感のあるリズム展開を見せます。冒頭は狭い配置のニ短調和音(D-F-A)で開始し、そこから旋律がじわじわと半音階的に拡張していきます。この過程は音価の伸縮を伴い、徐々に音域とリズムの振幅が拡大することで緊張が高まり、再び収束して主調に戻る構造です。これは数学的には「中心から外側へ広がり再び収束する」波形のように捉えられ、拡張と収縮という対称的なリズム曲線を描いていると言えます。また舞曲も第1番と同様に二部形式の対称性を保ちますが、特にこの組曲のサラバンドではゆったりした3拍子の中に拡張されたシーケンス(動機のくり返し展開)が含まれており、重厚なリズムが特徴です。
旋律の幾何学的パターン: 第2番の旋律は短調特有の半音階的な動きが増え、幾何学的には螺旋状に音域が広がるようなパターンを示します。プレリュードでは最初は狭い範囲に留まった旋律ラインが、徐々に上下に広がりを見せ(音程の拡大)、頂点に達した後は元の音域に戻ってくるため、全体として山なりの曲線を描きます。この「拡大と収束」の旋律パターンは自己相似的でもあり、小さな動き(例えば二音間の半音進行)を拡大コピーしたような大局的フレーズが確認できます。クーラントなど速い舞曲では跳躍を伴う音形が登場し、音型の形状はジグザグした折線のようにも捉えられますが、これらも繰り返し現れるモチーフとして図形的な秩序があります。
調性の分布と数学的変換: ニ短調の調性ゆえに、音の分布には短調特有の色彩が現れます。統計的に見ると、長調では頻出する長3度音程(例えばト長調でのB–Gなど)が、本組曲では短3度音程(例えばニ短調でのF–D)が多く出現する傾向があります。またプレリュード中盤では属調のイ短調や同主長調のニ長調などへの転調が織り込まれており、これは調の空間における移動と見做せます。これらの調性変換はバロック音楽のセオリーに従いつつも、第1番に比べて半音階的(クロマチック)な経過音が増えるため、音高分布のヒストグラムで見ると音階外音も含めた広がりが大きくなります。要するに、第2番は調性的にも第1番より複雑な分布を持ち、暗い短調の中に一時的な長調の明るさが垣間見える構造になっています。
フーリエ解析による周波数特性: 第2番プレリュードの音響的な特徴として、冒頭部分の密集和音→拡大→収束という変化は、時間信号としてみると低周波成分のうねりとして現れます。拡大していく過程では音の動きが速まり半音階的な細かな動きも増えるため、高周波成分の含有量が一時的に増大します。そしてクライマックスを過ぎ再び静まる部分では高周波成分が減り、低周波成分が優位になります。このように時間周波数解析的に見ると、第2番は周波数スペクトルが時間とともに大きく変動するのが特徴です。また全体のリズム構造をスペクトルで見ると、第1番同様に1/fに近い自己相似的傾向は持ちつつ、半音階的緊張感に由来するスペクトルのばらつき(ホワイトノイズ的成分の増加)が多少なりとも見られると推測されます。言い換えれば、第2番はスペクトル上で低周波の安定成分と高周波の不規則成分が交互に現れ、緊張と解放を周波数面でも表現しているのです。
第3番 ハ長調 (BWV 1009)
リズムの周期性と対称性: 第3番のプレリュードも16分音符の連続による軽快なパッセージで始まり、基本的な周期性は保たれています。ただし中間部では低音G音の持続(ペダル・ポイント)が強く打ち鳴らされ、緊張感が高まる独特のリズム効果があります。この反復する属音Gのリズムは一定の周期で現れるため、構造的には定常的な周期成分ですが、その上に乗る不協和音的なフレーズが進むにつれ心理的な緊張が増す仕組みです。ブーレIではAABというリズム・フレーズ構造が現れ、短いリズム単位(A)が2回繰り返された後にそれらの2倍の長さのフレーズ(B)が続くパターンが階層的に組み込まれています。このAABパターンの反復は楽曲内でスケール(時間尺度)を変えて何度も現れ、自己相似的なリズム対称性(いわばフラクタル構造)を形成しています。実際、ブーレIの最初の16小節を分析すると、小節レベルからフレーズレベルまで4段階の入れ子構造でAABパターンが確認できると報告されています。
旋律の幾何学的パターン: 第3番は旋律面でも自己相似の幾何学が垣間見えます。ブーレIのフレーズ構造は上述の通りカントール集合にも例えられるフラクタル性を帯びていますが、これは旋律の動きにも対応しています。例えばAセクションの短い音形が拡大されてBセクションの長い旋律線となり、それがさらに大きな構造で反復される様子は、旋律が異なる尺で同じ形状パターンを繰り返していると捉えられます。またプレリュード後半では、連続する16分音符の流れが一旦中断され、和音の急旋回(突然の和音連打)によって長い音価が挿入されます。この部分では旋律線が途切れ途切れになり、図形的にはそれまで一直線に近かった軌跡に大きなくぼみが生じるような変化があります。さらにプレリュードの結尾近くでは長大な上行音階が現れ、音高が一直線に高みに向かう直線的パターンを描きます。これら多様な形状が組み合わさり、第3番の旋律は全体として複雑な幾何学模様を形作っています。
調性の分布と数学的変換: 第3番ハ長調は安定した長調ですが、中でも特筆すべきは調性的に遠い転調が組み込まれている点です。例えばサラバンドでは後半で突然ニ短調という遠隔調に転じます。単旋律でこれほど遠い調に移行するには高度な工夫が必要ですが、バッハは音の曖昧さ(例えば導音を意図的にぼかす等)を利用して滑らかに調をシフトしています。このような調性の変換は音楽的には即興的で予期せぬ旅路のように聞こえますが、理論的には単一旋律に潜む複数の和声解釈を巧みに用いた数学的な離調操作と見做せます。また、第3番の終曲ジーグでは各部で意図的な不協和音のぶつかり(クラッシュ)が仕込まれており、これは伝統的な和声進行からの逸脱として調性的安定を一時的に揺るがします。これも一種の変換で、安定→不安定→安定という位相の反転を体現しています。
フーリエ解析による周波数特性: 第3番プレリュードのスペクトルを見ると、低音Gのペダルポイントが繰り返し出現するため、その反復周波数(およそ小節単位の周期に対応)は顕著なピークとして表れるでしょう。一方、その上で動く旋律は緊張が高まるにつれて装飾音や不協和音が増すため、高周波成分(急激な音程変化に対応する成分)も増えていきます。したがってスペクトル密度は当初は安定した低次成分が卓越しますが、中盤では広帯域にエネルギーが広がる傾向を示すと考えられます。ブーレIの自己相似構造は、もし音符出現頻度を周波数解析すればスケーリング則として現れる可能性があります。つまり、小さなスケールの繰り返し(Aパターン)と大きなスケールの繰り返し(全体のAAB構造)がそれぞれ固有の周波数ピークを持ち、それらがべき乗則的な関係でスペクトルに現れると予想できます(実際、バッハのチェロ組曲にはパワー法則的なスケーリングが存在し、顕著な例はフラクタル的とも評されています)。このように第3番は、時間領域でも周波数領域でも自己相似性と緊張・解決のダイナミクスが刻まれているのです。
第4番 変ホ長調 (BWV 1010)
リズムの周期性と対称性: 変ホ長調の第4番は、チェロにとって調性的に扱いづらい(開放弦を活用しにくい)調ですが、バッハはリズム面でも工夫を凝らしています。プレリュード冒頭は低音から高音への2オクターブ跳躍という大胆な出だしで始まり、以降は8分音符の持続的な一定拍動と、不定形なカデンツァ風パッセージ(自由なリズム)の挿入が交互に現れます。つまり規則的周期と非周期的な遊びが交替する構造で、数学的には基本波に対してランダムなインパルスが加わるようなリズムと言えます。この自由リズム部分は演奏上即興的解釈が可能で、全体の対称性を意図的に崩すことで却って曲に豊かな表情を与えています。一方、アルマンド以下の舞曲は他の組曲同様に二部形式の対称を保ちます。ブーレIIでは低音パートと高音パートがずれた形で同時進行し、高音が低音にわずかに遅れて追随するようなリズムが特徴的です。これは数学的には二つの波形の位相がずれた状態とも解釈でき、低音と高音のリズム的位相差が独特のゆったり感を生み出しています(同時代のマッテゾンはブーレを「やや緩慢で物憂げ」と評しましたが、このリズム構造がまさにその雰囲気を作っています。
旋律の幾何学的パターン: 第4番の旋律でまず目を引くのは、冒頭の2オクターブ跳躍という大きな音程移動です。これは旋律線上で垂直に大きく飛ぶようなもので、グラフに描けば一点からいきなり遠方まで線が跳ぶような鋭角的パターンです。この大胆な跳躍以降は、一転して細かな音階進行と持続音が組み合わさり、低音ではほぼ絶え間なく音が鳴り続け(これが連続する低音線=事実上の伴奏のような役割を果たします)、高音旋律はその上で掛留(サスペンション)音を多用して滑らかに進行します。
掛留とは一時的不協和を含む横の進行パターンであり、数学的には高音パートが低音パートに対し遅れた位相で波打つようなものです。この結果、サラバンドなどではチェロ一台ながらほとんど二声のポリフォニーが聞こえるほど密なテクスチュアになっています。
旋律線自体は緩やかな音階やアルペジオが中心ですが、所々に挿入されるカデンツァ風の急速なパッセージは渦巻き状の曲線を描き、一種の**渦(エディ)**のように全体の幾何学模様に変化を与えています。
調性の分布と数学的変換: 変ホ長調はチェロの開放弦(C、G、D、Aのうち)と調号が一致しない音が多いため(主音変ホや属音変ロは開放弦になく、運指が難しい)、音の分布は他の組曲に比べて独特です。音域的にも第4番では演奏上難しいポジションに踏み込むため音の配置(統計分布)は広範囲ですが、その代わり開放弦の共鳴による突出した強度の音は少なく、全体に音量・音色が均質になる傾向があります。調性的には変ホ長調から属調変ロ長調、下属調変イ長調など近親調への転調は含まれるものの、他の組曲に見られたような遠隔調への大胆な転調はあまりありません。むしろこの組曲のハーモニー上の特徴は、単一調内での多重和音と掛留による和声遷移です。サラバンドではほぼ全編にわたり低音が主和音の構成音を保持し続けることで調性の土台を築き、上声でII転換やVII和音の掛留が次々に現れては解決する、という形で和声的な張力を内部生成しています。このような和声進行の取り扱いは、数学的に見れば調性内での和音間の軌道(状態遷移)をデザインしているとも言え、調の枠組み自体は変えずにその内部構造を複雑化するアプローチです。
フーリエ解析による周波数特性: 第4番の音響特性は、「定常的な基本パルス + イレギュラーな高速パッセージ」という組み合わせに表れています。プレリュードの8分音符連打部分では一定周期の強い成分がスペクトルに現れますが、間歇的に挿入される高速パッセージは短時間に多くの音が詰まっているため、広帯域の周波数成分(ノイズに近いスペクトル)を一時的に発生させます。この結果、全体のパワースペクトルを見ると低周波のピークに加え高周波成分のブリップが点在するような形になるでしょう。さらにサラバンドやブーレで見られた持続低音+掛留の箇所では、低音が持続することでほぼDC成分に近い極低周波のエネルギーがあり、高音はそれに遅れて追従する周期振動(掛留の周期的発生)としてやや高い周波数成分を持つという、二峰性のスペクトル構造が局所的に生まれます。これは二つの異なる周波数の重ね合わせで、一種の振幅変調あるいは周波数分割のようにも解析できます。また、変ホ長調という調性上、他の長調に比べて高次の倍音(オーバートーン)が共鳴しにくいため、音色スペクトル上も特定の周波数が強調されにくいという特徴があります。すなわちスペクトル密度が比較的滑らかで、突出したフォルマントが少ない傾向があると推測されます。
第5番 ハ短調 (BWV 1011)
リズムの周期性と対称性: 第5番は他と大きく異なり、スコルダトゥーラ(調弦の変更)を採用しています(第1弦AをGに下げる)。プレリュードはバロックのフランス風序曲形式で、ゆったりとした付点リズムの序奏部と速いフーガ風の主部から成ります。序奏部では長短の付点音符が重厚な長短周期パターンを作り出し、これが厳かな雰囲気と低頻度の周期性を生みます。対照的に主部では16分音符の連続による高速で均一な周期に転じ、リズムの粒度が一気に細かくなります。この二部構成により、全体として二種類の異なる周期構造が対比される形になっています。舞曲では、アルマンド以下は他と同様に二部形式ですが、ガヴォットI・IIが用いられている点が特徴的です。ガヴォットIでは2拍子系の軽快なリズムの中で小節の強拍ごとに重音が置かれ、主拍にアクセントを与える周期的な強調が際立ちます。この定型的なリズムの繰り返しは周期関数にパルス信号を畳み込んだようなもので、各小節の頭にディラックの針(重音による強調)が打たれるイメージです。結果として、第5番のリズム構造は序曲部・フーガ部・舞曲部で各々異なる周期性を示し、全体では多層的な周期パターンの組み合わせになっています。
旋律の幾何学的パターン: 第5番の旋律面でまず注目すべきは、序曲部の重音を交えた荘重な旋律と、続くフーガ部の対位法的旋律の対比です。序曲部では4声の和音が頻繁に用いられ、旋律線は分散和音をなぞるように進行します。音価の長短も交互に現れ、譜面的には階段状の段差を持つ折れ線グラフのようです。フーガ部では単旋律ながら主題が時間差で何度も現れ、あたかも2声・3声が追いかけあっているような錯覚を起こさせます。これはテーマが異なる高さで再現される(例えばまず主音のCで提示され、次に属音Gで再現される、等)ことによるもので、旋律パターン的には同じ形状が鉛直方向(音高方向)に平行移動して繰り返される様子が見て取れます。いわば翻訳(トランスレーション)対称の原理が働いており、これはフーガにおけるテーマの移調再現そのものです。またサラバンドでは、全曲中でも特に有名な静謐な瞬間が訪れます。ここでは音の動きが極度に減衰し、ほぼ一音ずつ区切られるような「ため」があります。旋律的には溜め息のような下行二音の動機(長二度下降など)が連続して繋がり、全体としてじりじりと下降していく長いフレーズを形成します。これはグラフで言えば、小さな下降ラインが次第に連結して大きな下降トレンドを描いていく形状です。そして最後の音だけ突然上向して終わるため、直前まで続いた下降パターンを反転(上下対称)させたような印象的効果を生みます。この対称性の破れとも言える仕掛けによって、音楽的には時間が止まるような独特の余韻が作り出されています。ガヴォットでは重音を交えた跳ねるような主題が登場し、音程的にも反復跳躍が多用されるため、旋律線はギザギザとした波形パターンを示します。しかしこの主題も2つのガヴォットを通じて繰り返し扱われるため、全体としては統一的な図形(テーマの変形と回帰)が感じられます。
調性の分布と数学的変換: ハ短調の第5番は、調号に変化記号が多く含まれる関係で音高分布が他より広範に及びます。スコルダトゥーラにより開放弦AがGに下げられたため、曲全体でG音(属音)の存在感が増し、Gが共鳴弦としてしばしば鳴り響きます。これは統計的に見ればG音出現頻度の増加として現れるでしょう。またプレリュード後半のフーガでは、主題がハ短調で提示された後、しばしば属調のト短調や下属調のヘ短調などで再現されます。これは調性の移動(移調)が構造的に組み込まれている例で、楽譜上は異なる調に写った同一主題が見られます。終始短調で進行するため全体の調性感は暗く統一されていますが、終曲ではピカルディ終止(最後をハ長調和音で終わる)をとらず純粋な短調で締めくくられます。そのため各楽章の調性分布も、他の組曲に比べて長調への切り替えが極力抑えられているのが特徴です。唯一の例外はサラバンドで、後半に変ホ長調(同主長調)への一瞬の転調がほのめかされます。しかしこれはすぐに打ち消され、最後はハ短調に回帰します。これらは調性空間内の微細な動きとして捉えられ、調号こそ変わらないものの和声進行上で一時的に長調の和音が挿入されるといった局所的な変換が行われています。総じて、第5番の調性設計は短調の枠内で多彩な和声を紡ぎ出しつつも、調そのものは固定し続けるという一種の不変性を保っており、この点も他の組曲との対照を成しています。
フーリエ解析による周波数特性: 第5番プレリュードは序曲部とフーガ部で大きく様相が異なるため、それぞれの周波数特性も分けて考える必要があります。序曲部では付点リズムによる重厚な低頻度パルス(ゆっくりとした強拍)が支配的で、スペクトル上はきわめて低い周波数帯域にエネルギーが集中します。一方フーガ部に入ると16分音符の連続によって高頻度の等間隔パルスが生まれ、一挙に高周波成分が増大します。この切り替えはスペクトル上では低周波成分の減衰と高周波成分の立ち上がりとして表れ、第5番全体のパワースペクトルは2つの異なる帯域にピークを持つ二峰性になると考えられます。これはまさにフランス風序曲の二重構造を周波数領域で写像したものと言えます。またガヴォットで各拍に置かれる重音は、時間的には周期的なインパルス列となり、その基本周波数(拍ごとの周期の逆数)がスペクトルに明瞭に現れるでしょう。同時に重音そのものは複数の音の和音であるため、その瞬間瞬間には広い周波数帯域(各構成音に対応する周波数)が励起されます。つまりガヴォットでは時間的周期性(リズム)と周波数的広帯域(和音)が同時にスペクトル上に存在することになります。さらにスコルダトゥーラにより開放弦Gが増えた影響で、楽器の共鳴特性にも変化があります。通常のチェロよりもG音(約196Hz)に対応する成分が鳴りやすくなるため、演奏全体の周波数スペクトルでもその近傍周波数成分が相対的に強調される可能性があります。こうした要因により、第5番の周波数特性は低音域の共鳴と多声的テクスチュア、高速パッセージの混在する複雑で豊かなスペクトルを呈しているといえるでしょう。
第6番 ニ長調 (BWV 1012)
リズムの周期性と対称性: 第6番は5弦チェロ(あるいはチェロ・ピッコロ)向けに書かれており、高音域の拡張が特徴です。そのため他の組曲以上に音数が多く、リズム的にも華麗で輝かしい連続音型が目立ちます。プレリュードはニ長調の明朗さを活かし、連続する高速音型と開放弦の鳴動によって終始途切れない運動量を持っています。アルマンドは全6曲中最も長大で、しばしば32分音符の細かな装飾音形を伴う緩やかなテンポの舞曲です。音価が細分化される一方で大きな跳躍を伴うため、リズム的には不規則な間合い(例えば大跳躍前後でわずかな溜めを作る等)が必要となり、完全な等間隔とはいきません。しかし全体構造としては他と同様に二部形式の均衡は守られています。ガヴォットI・IIでは第5番と同様に2拍子系の舞曲リズムが用いられますが、第6番では音域が広いため各拍の中で音形が縦横に動き回ります。ジーグ(終曲)は全組曲中でも最も技巧的かつ熱狂的で、ほとんど休符のないペルペトゥーム・モービレ(無限運動)的リズムを持っています。その速い3連跳躍の継続は強烈な周期性を帯び、リズムスペクトル上は高い基本周波数成分が卓越するでしょう。総じて、第6番のリズムは高密度かつ広音域ゆえに変化に富みますが、各楽章の舞曲としての定型(アルマンドの4拍子、クーラント系の3拍子、サラバンドの3拍子強弱、ジーグの6/8的ノリなど)は守られており、その上で音数が増えたぶんだけスペクトルも高周波側にシフトしていると考えられます。
旋律の幾何学的パターン: 第6番では5本目の弦(上昇したE弦)が追加されたことで、旋律の到達しうる高さが飛躍的に伸びました。その結果、旋律線は他の組曲では考えられないような広大な射程を持ちます。アルマンドでは音域が高く拡張されたおかげで、まるで天上で漂うような浮遊感のある旋律が展開されます。具体的には通常のチェロの音域上限を超えた高音で主旋律が奏でられ、中低音はほとんど登場しません。これはグラフ上で見ると、旋律線が非常に高い音高帯域に偏って推移することを意味し、平均値から見ると上方へシフトした波形になっています。旋律の形状自体はバロック舞曲の伝統に沿った音階的・分散和音的なパッセージですが、高音域での分散和音は物理的制約から大きな跳躍を伴うものが多く、音形は鋭角で山谷の幅が大きい折れ線に似ています。サラバンドでは重音を含む和音が随所に要求され(5弦の利点を活かした広い構成音)、単音で演奏可能な和音が多用されます。そのため旋律線も時折和音を形成するために分岐し、一時的に二声のポリライン(二本の折れ線グラフ)が重なって走るような状態になります。ジーグの旋律は三連符を基調にめまぐるしく上下し、3オクターブ以上の音域を駆け上がり降りるといった大スケールのジグザグを描きます。これら全て、5弦という拡張により可能となった広範な幾何学模様であり、第6番の旋律はまさに縦横無尽な図形と言えるでしょう。
調性の分布と数学的変換: ニ長調の第6番は、調性的には比較的オーソドックスで明るい響きを持ちます。第5番とは対照的に全曲にわたり長調の輝きが保たれ、遠隔調への寄り道はほとんど見られません。むしろ特徴は調性というより音域分布に現れます。統計的に見ると、第6番では高音E弦の追加によって利用可能音高が増えたため、音の頻度分布は他の組曲に比べて高音側に裾野が広がった形になります。実際、第6番では最高音が他の組曲より長2度(全音)以上高く、最低音(開放CまたはD)との差は3オクターブ以上に及びます。このため音高ヒストグラムを作れば、低音域から高音域までほぼ切れ目なく分散した分布が得られるでしょう。調的変換という点では特筆すべき例は少ないものの、第6番ではシーケンス(順次進行)の上昇度合いが他より顕著です。つまり動機を繰り返すごとに音高が段階的に上がっていく箇所が多く、これは5弦のおかげでより上方へ進めることから可能になった現象です。この順次進行上昇は音楽のクライマックスを築く技法ですが、数学的にはフレーズを一定の音程で並進移動し続ける操作であり、転移行列的な処理とも捉えられます。第6番ではそれが他以上に大胆に行われています。また5弦により開放E音(ミ)が追加されたことで、和声的にはIVの和音(ト長調)やIIの和音(ホ短調)の響きが強調できるようになっています。これらは調性内の和音選択肢を増やす効果を持ち、曲全体の和声進行に新たなパスを提供しています。結果として、第6番は伝統的なニ長調の枠組みを保ちつつも、音域拡張による垂直方向(音高方向)の拡大という点で他の組曲と一線を画しています。
フーリエ解析による周波数特性: 第6番は音域・音数とも最大であるため、その時間周波数特性も非常にリッチです。プレリュードやジーグのような高速連続音では、スペクトル上高周波数までエネルギーが充満し、広帯域のパワースペクトルを示すでしょう。一方、アルマンドのようなゆったりした楽章でも跳躍が大きいため低周波域だけでなく中高周波域にも成分が散在すると考えられます。特筆すべきは、追加された第5弦がもたらす倍音スペクトルの拡張です。5弦のチェロは通常の4弦よりも高次の倍音を多く含む傾向があり(E線自体の固有振動数が高いため、それに付随する倍音群も高周波側に広がる)、楽器から放射される音響エネルギーの周波数分布も高音側にシフトします。また第6番のジーグでは約3オクターブの音域飛翔があるため、周波数領域では約2倍の周波数比を持つ音高(オクターブ差)が同時期に現れることになります。これはスペクトル上で調波(高調波)の重なりを生み、ある音の高調波成分と他の音の基音成分がぶつかることでスペクトルにおける共鳴ピークが形成される可能性があります。さらに、高音域での強い発音は耳にも鋭い印象を与えることから、時間的には瞬発的でも周波数軸では局所的な高エネルギー点となります。総合すると、第6番のフーリエスペクトルは低音から高音まで裾野が広がった帯域の広い1/fノイズに近い形状になると推測できます。言い換えれば、全周波数帯にわたりエネルギーが分布しつつ、低周波から高周波まで滑らかに減衰していく勾配(指数的なスペクトル傾斜)を持つと考えられます。この傾向は人間にとって心地よいバランス(ランダムさと秩序の調和)をもたらすとされ、第6番の豊かで堂々とした響きはまさにそのスペクトル特性によって支えられていると言えるでしょう。
まとめとユニークな解釈
以上のように、バッハの無伴奏チェロ組曲1番から6番は、各々が固有の数学的個性を持ちながら全体として統一された美を形成しています。リズム面では、全曲に共通する周期的安定性と各曲固有の対称性の遊び(例えば第3番ブーレのフラクタル対称性や第5番サラバンドの対称の崩し)が見られます。旋律面では、音型の幾何学的パターンが各曲で異なる様相を呈し、第4番のような大胆な跳躍から第5番のような沈潜する下降形まで多彩ですが、いずれもバッハの内在する対位法的思考に裏打ちされた構造美を宿しています。調性的には、長調と短調の対比、調内・調間の変換操作がドラマを生み、第3番や第5番のように遠隔調や複雑な和声を取り入れた例から、第6番のように調性自体は保ちつつ音域拡張で新機軸を打ち出す例まで、音楽空間における座標移動とも言うべき工夫が凝らされています。さらにフーリエ解析的視点では、各組曲のフレーズ展開や音符密度がスペクトル上に独特の指紋を残しており、第1番・第6番のような1/f的自己相似スペクトルから、第2番・第5番のように二峰性のスペクトルを持つケースまで、聴覚的にも数学的にも興味深い差異が浮かび上がります。このような分析から導かれるユニークな解釈として、バッハの無伴奏チェロ組曲は単なる音楽作品に留まらず、数学的構造美の実験場であったとも言えるでしょう。バッハ自身が意図的に数学原理を用いたかは定かではありませんが、結果的に彼の音楽にはフラクタル的自己相似構造や1/fゆらぎといった普遍的な数理パターンが刻印されています。これは「音楽は数学の音を伴う繰り返しである」という言葉を体現するものでもあり、バッハの天才的直感が数理的真理に触れていた可能性を示唆します。したがって、本分析で浮かび上がった各組曲の特徴を踏まえると、演奏解釈においても単に音符を追うだけでなく、その背後にある数理的な対称とバランスを意識することで、新たな洞察が得られるでしょう。例えば、第3番ブーレIをフラクタル構造になぞらえてフレーズのスケール感を強調したり、第5番サラバンドで下降動機の反復から最後の上昇への対称性の破れを際立たせたりといったアプローチです。
バッハの無伴奏チェロ組曲は、音楽と数学が出会う深遠な領域で輝きを放つ作品群です。その一つ一つを数理的に眺めることで、私たちは音楽美の新たな層を発見でき、そして改めてバッハの創造性に驚嘆させられるのです。