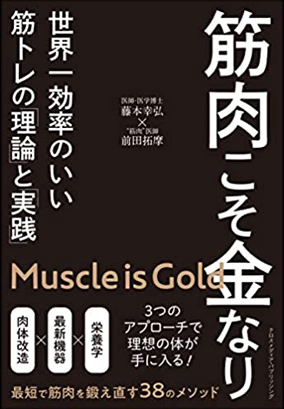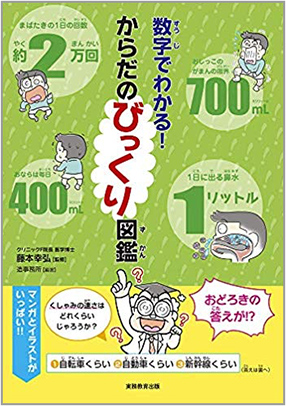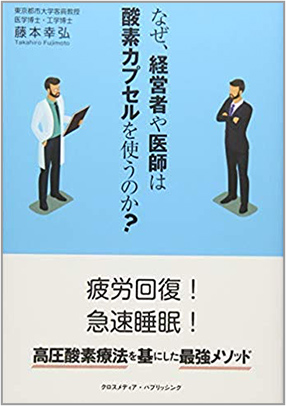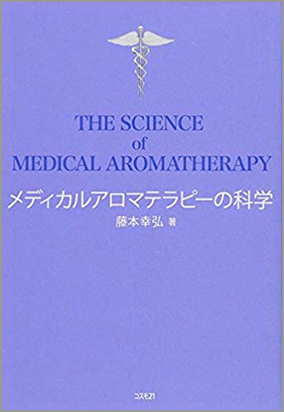来たー!日本人がF1で勝てるチャンス。

角田裕毅、レッドブル電撃昇格で日本人初PP&初Vに期待/F1(サンケイスポーツ)
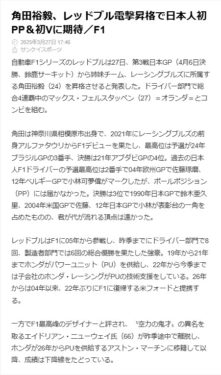

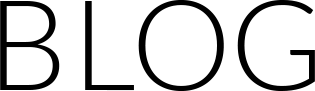 藤本幸弘オフィシャルブログ
藤本幸弘オフィシャルブログ

会食にちょっと早めに着いて目黒川へ。

川に向かう桜の木が綺麗だったのに、切られてしまったんですね。
桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿。
しかも全然空いてるのに、警備員が立ち止まらない、止まって写真は撮るなと声を張り上げています。
大きなカメラ持った外国人が不思議そうにしてました。
20年前のルーブルの「No Flash」を思い出しました。
そう叫ぶ声のが五月蝿いっちゅうの。




ビタミンB群考――疲労回復とミトコンドリア、アンチエイジング物質NMNとの関わり

ビタミンB群と一口に言っても、それは1つの物質ではない。ビタミンB1からB12まで、それぞれがまったく異なる構造と機能を持ちながら、代謝というひとつの大きなオーケストラを指揮している。それらを総称して「ビタミンB群」と呼ぶこと自体、ある意味では栄養学的便宜であり、だからこそ個別の役割をきちんと理解する必要がある。
まずビタミンB群の最大の特徴は、補酵素(コエンザイム)として代謝に深く関与することである。糖質・脂質・タンパク質の三大栄養素をエネルギーに変える過程には、必ずと言っていいほどビタミンB群が登場する。つまり、これが不足すればどれほど高栄養の食事を摂っても“燃やす”ことができない。
たとえば、B1(チアミン)は糖代謝に不可欠で、TCA回路に入る前の「ピルビン酸→アセチルCoA」の変換に関わる。B2(リボフラビン)はフラビン酵素群(FMN, FAD)を構成し、電子伝達系の主役。B6(ピリドキシン)はアミノ酸代謝の要であり、B12や葉酸はDNA合成と深く関わっている。
このように、ビタミンB群は細胞の“発電所”であるミトコンドリアの円滑な運転に不可欠な潤滑油であると言ってもよい。加工食品中心の食生活では、エネルギーを摂ってもビタミンB群が足りず、“燃えない疲労”や“隠れ栄養失調”に陥ることがある。
加えて、ビタミンB群は互いに協調して働くため、単独摂取ではなく複合摂取が原則である。市販されているBコンプレックス製剤には、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸などがバランスよく含まれており、ストレスや疲労が強い時の補助に適している。特にB6・B12・葉酸の三者は、ホモシステイン代謝に関与し、動脈硬化のリスク軽減にも注目されている(Homocysteine Lowering Trialists’ Collaboration. BMJ. 2002;325(7374):1202)。
しかし注意すべきは、B群はすべて水溶性であるため過剰分は尿中に排泄されるという点だ。「黄色い尿=無駄になっている」と言われることもあるが、それは一部でしかない。むしろ、体が必要な分だけ使って残りを排泄するという“調整可能なビタミン”であるという見方の方が正しい。
近年では、B群をミトコンドリア活性化の観点から再評価する研究も進んでおり、抗老化、神経保護、さらにはうつ病や慢性疲労症候群における補助療法としても検討されている(Kennedy DO. Nutrients. 2016;8(2):68)。
ビタミンB群と聞いて、最初に思い浮かべるのは「疲労回復」かもしれない。しかし、B群は単なる滋養強壮剤ではない。細胞の“燃焼炉”であるミトコンドリアにとっては、不可欠な補酵素であり、神経・皮膚・造血・DNA合成といった極めて多彩な役割を果たしている。
中でもビタミンB3(ナイアシン)は、その歴史において人間の精神に深く関わってきた。アメリカ南部では20世紀初頭、「ペラグラ(Pellagra)」と呼ばれる奇病が社会問題となっていた。皮膚炎・下痢・認知障害を三徴とし、最終的には死亡に至る病。南部の貧困層に多発し、一時は感染症や遺伝病と考えられていたが、1915年にジョセフ・ゴールドバーガー博士が「これは栄養失調、特にトウモロコシ中心の食生活によるナイアシン不足である」と指摘。ペラグラの患者に肉や酵母を与えたところ症状が改善し、その原因がB3欠乏症であると判明した(Goldberger J. Public Health Reports. 1915)。この発見は、栄養不足が精神病を引き起こすという認識を医療界に広めた。
実はナイアシンは、現代の精神医学でも注目されている栄養素のひとつだ。かつてノーベル賞候補にも挙がった精神科医エイブラム・ホッファーは、統合失調症の患者にナイアシン大量投与を行い、一定の改善効果を報告している(Hoffer A. Int J Neuropsychiatry. 1966)。もちろん科学的議論は続いているが、「ビタミンB群が心に効く」という知見は今なお臨床で活きている。
そして現代。B群の中でもB3の代謝産物として生まれたNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)が、アンチエイジング研究の最前線に登場してきた。NMNは体内でNAD+に変換され、ミトコンドリアでのエネルギー産生やサーチュイン活性化に関わる。これは老化やDNA修復、さらには概日リズムに関与するとされており、ビタミンB3の“高次代謝物”としての機能を再定義しつつある(Yoshino J et al. Cell Metab. 2011;14(4):528–36)。
ただし、NMNは薬品ではなく、あくまで補助的な栄養成分である。日常でB群を補う場合には、やはりBコンプレックス(複合製剤)としての摂取が基本だ。B1(糖代謝)、B2(脂質代謝)、B6(神経伝達)、B12・葉酸(造血・DNA合成)などが連携してこそ、初めてその“代謝の交響楽”は響く。
また、B群はストレス応答やホモシステイン代謝にも関わるため、心身のバランス維持にも重要である。現代のような高ストレス社会では、B群不足が慢性的な疲労感や集中力低下の原因となることも少なくない。
⸻
ビタミンB群とは、代謝の根幹に関わる「静かなマエストロ」であり、かつてペラグラで苦しんだ人々の心も、NMNを介して未来の寿命延伸に挑む現代科学も、すべてその延長線上にある。
僕たちが日々の中で何気なく摂っている栄養素の奥に、これだけの“知的な物語”が広がっているという事実は、やはり驚嘆に値する。
脚気とビタミンB1が動かした日本史

文士森鴎外の医師としての蹉跌
脚気が将軍を殺し、国家の兵を滅ぼしたことをご存知ですか?
この一文は決して文学的比喩ではなく、科学的事実である。脚気――ビタミンB1欠乏によって起こる神経疾患であり、心不全を伴うこともある重篤な病。この病が、日本の政治体制と軍事力に深く影響していたことは、意外に知られていない。
たとえば幕末、わずか20代で病没した第14代将軍・徳川家茂。彼の死因は当時「脚気衝心(心不全型脚気)」とされていた(日本医史学雑誌 1995年 第41巻 p.135-142)。上洛中、白米中心の食生活を続けた家茂は、日々の政務と移動による過労も重なり、ついに京都・二条城で倒れた。将軍の死が徳川幕府終焉の一端を担ったと考えるならば、脚気はまさに政権の瓦解に寄与した「見えざる死神」であった。将軍が白米でなく、ビタミンB1が含まれていた玄米を少しでも食べていたら、歴史は変わっていただろう。
しかし、脚気の悲劇はそれだけでは終わらない。明治37年の日露戦争。最前線の陸軍では約4万人の兵士が脚気で死亡している。これは戦死者とほぼ同数に及び、戦場よりも飯ごうの中にこそ、兵士の命を奪う本当の敵がいたことを示している(軍事医学 1982年 第39巻 p.211-220)。
なぜここまで脚気が蔓延したのか?そこには、海軍と陸軍の食事方針と医学思想の分岐があった。
海軍では、イギリス帰りの軍医・高木兼寛が中心となり、洋風食を導入。パン・肉・牛乳・野菜を含む献立で脚気の予防に成功した。実証的アプローチで得られた「栄養が脚気を防ぐ」という仮説は、海軍内で評価され、実際に脚気発症率は激減した(日本栄養・食糧学会誌 1999年 第52巻 p.301-310)。
一方の陸軍では、ドイツ医学に傾倒した軍医総監・森林太郎(森鴎外)が、脚気を感染症とする仮説に固執。白米中心の食生活を改めることなく、検疫や衛生管理を強化するばかりであった(鴎外全集 第14巻 岩波書店 1972年 p.233-245)。結果、数万の若き兵士たちが、栄養失調によって命を落とすこととなった。
現代栄養学においては、ビタミンB1の重要性はもはや常識となっている。チアミンは糖質代謝に不可欠な補酵素であり、神経機能の維持にも重要である。B1は水溶性で体内に貯蔵されにくく、偏食やアルコール過多、また精製穀物ばかりの食生活では簡単に欠乏する。今日では、潜在性ビタミンB1欠乏が糖尿病患者や高齢者、ダイエット志向の若者に増加しているとされ、再び脚気の再来が危惧されている(『ビタミン』第94巻、2020年、p.203-209)。
実際、現代型脚気(いわゆるサブクリニカル脚気)は、疲労感、手足のしびれ、動悸といった非特異的な症状を呈し、見過ごされやすい。特に高カロリー・低栄養の食事をとる人々には、症状が進行するまで気づかれず、心不全や意識障害にまで至るケースもある。
このことから、現代においても「栄養は目に見えぬ兵器」であり、国家の健康を支えるインフラであることが明らかとなる。高木兼寛が『衛生提要』(1883)で述べた「病気は未病で防ぐ」という言葉は、現代予防医療の原点といっても過言ではない。
個人的には文士としての森鴎外の作品は好きで、中学生の時から何度も読み返してきた。一方で医学とは科学であると同時に、思想である。高木は実証を重んじ、森は理論に忠実であった。その差が、歴史を動かしたのである。
一人の医師の信念が、かたや数万の命を救い、軍隊の運命を変えた。
栄養と医療の狭間に立つ我々は、今こそ高木と森林という二人の巨人の対照から学ぶべき時である。
ビタミンの中でも、ビタミンC(アスコルビン酸)は最も知られた栄養素の一つであろう。水溶性であり、熱や光、酸素に対して極めて不安定であるがゆえに、その取り扱いには細心の注意が求められる。
驚くべきことに、哺乳類の多くは体内でビタミンCを合成できる。だが、人間と類人猿、モルモット、そしてコウモリや一部の魚類は例外である。ヒトのゲノムにおいて、ビタミンC合成の鍵となる酵素「L-グロノラクトンオキシダーゼ(GULO)」をコードする遺伝子はすでに失活しており、これは進化の過程で失われた“贈り物”とも言える(Nishikimi M, Yagi K. Subcell Biochem. 1996;25:17–39)。
かつて航海時代の船乗りたちは、長い航海の末に歯茎が腫れ、皮膚に内出血を起こし、最終的には死亡する奇病に悩まされた。これが壊血病(scurvy)である。ビタミンCが欠乏することで、コラーゲン合成が破綻し、毛細血管や皮膚、粘膜が脆弱化していく病態である(Hirschmann JV, Raugi GJ. Am J Med. 1999;107(6):534–6)。
壊血病の発見が、栄養学という分野を医学的に正当化した最初の出来事だったとすら言える。1747年、イギリス海軍医ジェームズ・リンドはレモンとオレンジが壊血病を予防することを臨床試験で示した。これは世界初の無作為化比較試験ともいわれている。そしてこの発見をもって、ビタミンCは“生命維持に不可欠な外因性物質”として歴史に刻まれることとなった。
ヒトがビタミンCを外部から摂取しなければならない理由は、単なる栄養素以上の役割にある。最大の特徴は「抗酸化作用」だ。活性酸素種(Reactive Oxygen Species:ROS)は、我々の体内で代謝の副産物として、あるいは紫外線や放射線、環境汚染などの外的要因によって発生する。これらは細胞膜の脂質、タンパク質、さらにはDNAをも損傷する。その代表的な例が、放射線被ばくに伴うDNAの二重らせんの断裂であろう(Hall EJ, Giaccia AJ. Radiobiology for the Radiologist. 7th ed. 2012)。
特に細胞分裂が活発な小児においては、そのダメージは取り返しのつかないものになりうる。こうした活性酸素に対し、ビタミンCは電子供与体として働き、自ら酸化されることでROSを還元し、無害な分子へと変換する。この「自己犠牲的」な抗酸化のメカニズムこそが、ビタミンCの真価である。
35歳までは人間もSOD(スーパーオキシドディスミュターゼ)活性が高いが、それが低下したのちは、ビタミンCはアンチエイジングには必須とも言える。
かのライナス・ポーリング博士は、ノーベル賞を二度受賞した希有な科学者でありながら、晩年はビタミンCの研究に傾倒した。その研究成果は医学界で賛否両論を呼んだが、彼の遺した著作は今もなお多くの臨床医にインスピレーションを与えている(Pauling L. Vitamin C and the Common Cold. 1970)。
しかし、現代の市場に出回るビタミンC製品には注意が必要である。食品添加物として用いられるビタミンC(酸化防止剤E300)は、食品の酸化劣化を防ぐためのものであり、人体への栄養供給を目的とはしていない。こうしたビタミンCはすでに酸化された状態で含まれている場合が多く、経口摂取しても本来の生理活性は期待できない。
そもそも、アスコルビン酸にはL体とD体という鏡像異性体が存在する。生体で活性を持つのはL-アスコルビン酸のみであり、D体は構造が似て非なる“偽ビタミンC”である(Arrigoni O, De Tullio MC. Biochim Biophys Acta. 2002)。市販の合成ビタミンCの中には、合成効率を優先してラセミ体(L体とD体の混合)で供給されているものも存在する。製品表示に「L-アスコルビン酸」と明記されているか否かは、最も基本かつ重要なチェックポイントである。
また、サプリメント界隈で近年話題になっているのがリポソーム化ビタミンCだ。脂質二重膜でアスコルビン酸を包み込むことで、腸管からの吸収効率を高め、血中濃度の上昇を図るという理屈である。確かに動物実験では有意な吸収向上が示された報告もある(Hickey S, Roberts H. J Nutr Environ Med. 2005)。しかしヒトを対象とした大規模なエビデンスはまだ少なく、効果は個体差も大きい。さらに、製造過程で使用されるリン脂質の質や安定性、酸化防止の技術によっても製品差が生じるため、すべてのリポソーム製品が“良い”とは限らない。現段階では「選ぶべき製品もあるが、過信は禁物」というのが現実的な評価だろう。
僕自身の臨床経験でも、リポソーム化によって胃腸障害を回避できた症例はあるが、皮膚やエネルギー代謝における顕著な差は製品ごとに大きく異なっていた。むしろ重要なのは、どの時間帯に、どの食品と一緒に摂るかといった基本的な栄養学的配慮である。例えば鉄分との同時摂取によって吸収が促進される一方、カフェインや高脂肪食との同時摂取では吸収が妨げられるという報告もある(Carr AC, Frei B. Am J Clin Nutr. 1999)。

結論として、ビタミンCを健康維持や医療的効果の観点で服用する場合、以下の要素を満たすことが望ましい。
• L-アスコルビン酸であること(D体を含まない)
• リポソーム化は選択肢の一つだが、製品の質に注意
• 1回500mg前後、1日3~6回に分けて摂取
• まずは新鮮な野菜・果物からの摂取を優先(赤ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類など)
まずは自然な食品から。足りない部分を薬で補充すべきという事ですね。