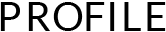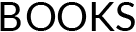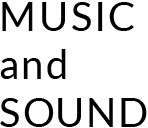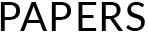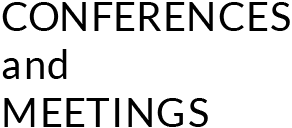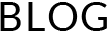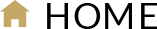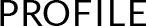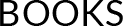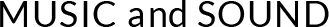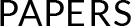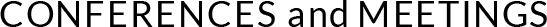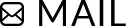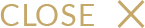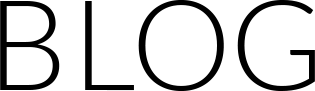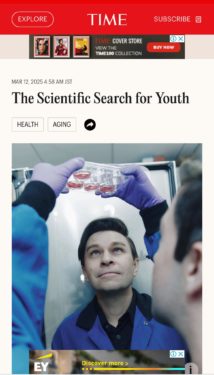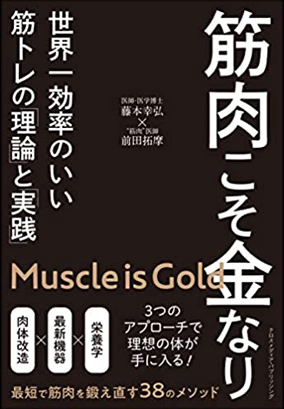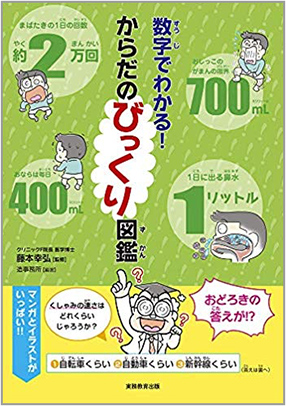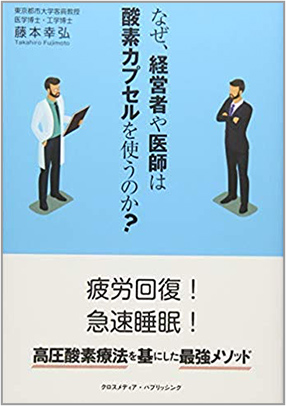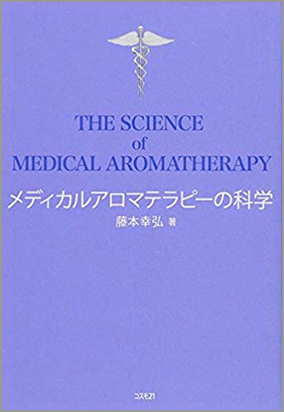Netflixで唐沢財前の白い巨塔の放映が始まった。第一話ワーグナーのタンホイザー序曲で始まる映像。

僕も専門医を取得したばかりの頃で、大学病院の医局人事の真っ只中にいたので、身が引き締まる思いで観ていました。
『白い巨塔』を初めて読んだ10代の頃、心を揺さぶられたのは、財前五郎の野心でも手術の腕でもなく、里見脩二の、患者を決して見捨てないというその誠実なまなざしだった。
だが、白衣をまとい、実際に医療の現場に立つようになってから、僕は気づいた。
「里見脩二は、ひどい医者である」という事実に。
もちろん、彼は誠実だ。患者本位であろうとする姿勢は崩さず、医局政治にも与しない。一見すると、それは医師の理想像である。
だが、彼の行動を医療現場の文脈で冷静に分析すると、その“正義”がいかに独善的で、時に無責任でさえあるかが見えてくる。
助教授という教育的・研究的責任を持ちながら、組織改革に内側から関与するのではなく、権力に反発し、“患者のため”という美名のもとに医局を去る。これは教育者としての責務放棄に等しい。
現実の医療において、個人の信念だけで体制を変えることはできない。
チームで動き、制度の中で最善を尽くすのが現代医療の根幹であり、里見のような振る舞いは、自己満足的なヒロイズムに過ぎないという厳しい評価すらある。
実際、臨床の第一線に立つ医師の多くは、ある時点でこのことに気づく。
医学生の頃は誰もが“理想の医者”を夢見る。
だが、現場に立ち、時間に追われ、訴訟リスクと向き合い、制度の複雑さと戦う中で、「誠実なだけの医師では現場を守れない」という現実に直面する。
そのとき、多くの医師が、里見像から静かに距離を取り始める。
やがて、「あの人は誠実だけど、一緒にチームは組みたくない」とすら口にするようになる。
一方で、財前五郎のように野心を持ち、組織を動かし、研究を牽引するタイプの医師が、現代医療においては“現場を維持する屋台骨”として必要不可欠であることも、次第に見えてくる。
彼のような存在がいなければ、最先端の医療技術も、臨床研究も、医療制度そのものも、前に進まない。
たとえその人物が傲慢で、自身の成功を強く欲していたとしても、それによって救われる患者がいるという現実は、医師として受け止めねばならない。
それでも、里見に心を動かされる若者がいる。
それは幻想であり、虚構に近いとしても、そのような“まっすぐすぎる理想”に一度は憧れる経験こそが、医師という職業を選んだ意味の一部でもあるのだろう。
大切なのは、そこにとどまらず、「理想の医師像」と「現実の医療者像」の間で、自分なりのバランスを見出すことだ。
それが、医師としての成熟であり、現実の患者を救うために必要な“現実的な理想”なのだ。
白衣をまとうということは、演劇の衣装ではない。
それは、他者の人生と命に対して、自らの限界と責任を知りながら、引き受ける覚悟に他ならない。
『白い巨塔』を愛した若き日の自分に、私は今こう語りかけたい。
里見にはなれなくていい。
だが、あの誠実さを、一度は信じたことを、恥じる必要はない。