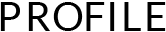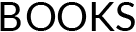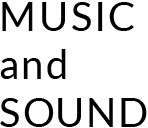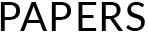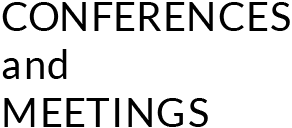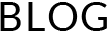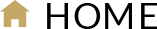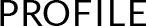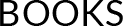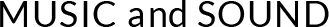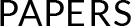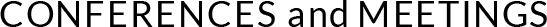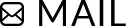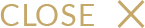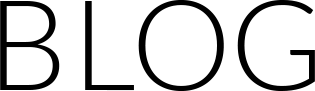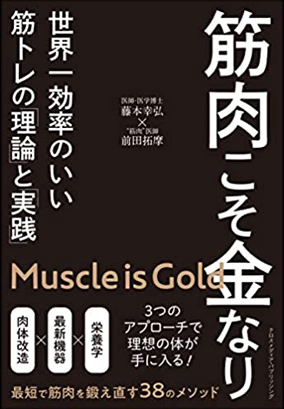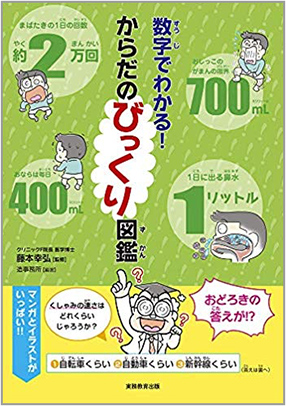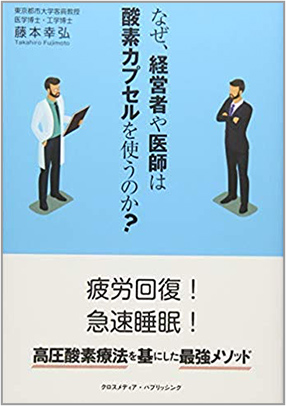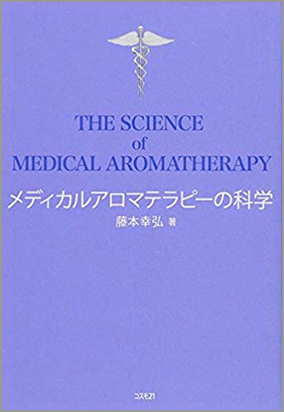『グレート・ギャツビー』(The Great Gatsby)という作品に、みなさんはどんな思い出をお持ちですか?
フィッツジェラルドがこの名作を世に送り出したのは、今からちょうど100年前、1925年4月10日のこと。
偶然にもその記念すべきタイミングに、僕はこの物語の舞台でもあるニューヨークの地に立っていました。なんとも運命的というか、不思議な縁を感じてしまい、その足でミュージカルのチケットを手に入れたのです。
この小説、英語圏では「アメリカ文学の至宝」とも言われ、モダン・ライブラリーの“20世紀最高の英語小説ランキング”では第2位にランクされています。でも、正直なところ、最初に読んだときの僕はそこまで深く心を動かされませんでした。高校生の頃に手に取ったのは、野崎孝訳(1974年)のもので、誠実で丁寧な訳だったと思いますが、どこか作品との距離を感じてしまっていたんですね。
そんな印象が大きく変わったのは、ずっと後、大人になってから村上春樹訳(2006年)を読んだときのこと。
敬愛する作家の手によるこのバージョンは、とても軽やかでスタイリッシュ。けれどもその奥には、ギャツビーという男の孤独や、報われない想いの切なさが、静かに、そして深く流れていて……気がつけばページをめくる手が止まりませんでした。
まさに「文体の魔術」と言うべきでしょうか。翻訳が、原作に新しい命を吹き込む瞬間に立ち会ったような気がしました。
けれどもこの村上訳、魅力的である一方で、翻訳研究の世界では少なからぬ議論を呼んでいるとも聞きます。特に話題になったのが、ギャツビーの車の描写なんです。
原文ではただ “yellow car” とあるだけなのに、村上訳では「ジャガー」と車種名が挿入されていて、僕自身も「あれ? 1920年代にジャガーってもうあったっけ?」と違和感を覚えたのをはっきりと覚えています。
実際、当時のアメリカではジャガーはまだ高級車としては広く知られておらず、他の翻訳者たち——野崎孝訳、小川高義訳(2009年)など——は「黄色い車」とだけ訳しています。そのため、「これは村上春樹の大胆な演出なんじゃないか?」という声が出るのも、無理はありません。
では、それは「誤訳」だったのか? それとも、時代を越えて読者に作品を届けるための「創造」だったのか。
そんな問いが自然と浮かび上がってきます。
翻訳って、ただ言葉を置き換えるだけの作業じゃないんですよね。読者の心にどう届くか、その響き方までを考える、とても繊細で創造的な行為なんだと思います。村上春樹というフィルターを通して読んだギャツビーは、僕にとってはじめて「生きたキャラクター」として立ち上がってきた。だからこそ、あの訳には深い意味があったんじゃないか、と今では思うようになりました。




さて、そんなことを考えていた折も折。2024年3月29日からブロードウェイで幕を開けた新作ミュージカル『The Great Gatsby』を観劇。これがまた、想像以上の体験でした。
ギャツビー邸の贅を尽くしたパーティーは、まばゆい照明と華やかな衣装のなかで見事に舞台化されていて、観客を1920年代の狂騒の渦へと巻き込んでいきます。演者たちの表情も実に細やかで、ギャツビーの内に秘めた痛みや、デイジーとのすれ違いに胸を打たれました。
そして何より音楽の生演奏。どこか懐かしい旋律の中に、現代的なアレンジが加わっていて、物語に新しい深みが生まれていたのです。舞台ならではの解釈が加わることで、物語の本質がより鮮やかに、そして繊細に浮かび上がってきたように感じました。
翻訳でも映画でも、そして舞台でも物語はそのたびにかたちを変えながら、現代の僕たちの前に再び姿を現します。100年という時を越えてなお、ギャツビーは変わらぬ声で、今を生きる我々に語りかけてくる。
その“再生”の瞬間に立ち会えたことに、心からの感謝を込めて、この筆を置きたいと思います。