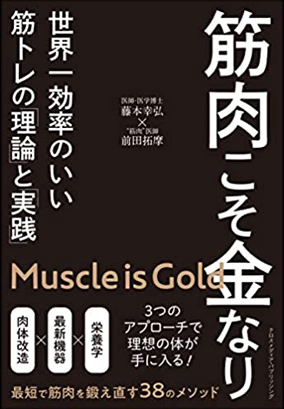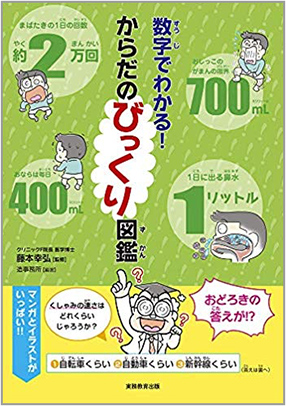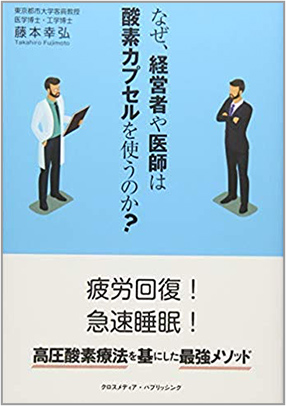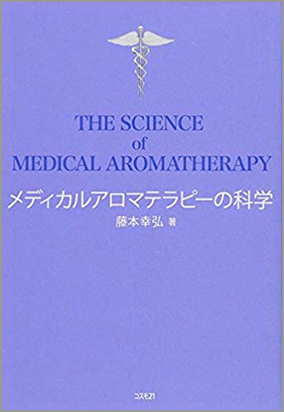ウクライナ問題のおかげで、北極ルートが一般的になりましたね。
ディプロマもらいました。



地球温暖化と言いつつ、最後の陸地を越えると極圏は、太陽こそ落ちませんでしたが、ほぼほぼ氷に囲まれていましたけれどね。

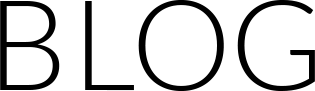 藤本幸弘オフィシャルブログ
藤本幸弘オフィシャルブログ

ウクライナ問題のおかげで、北極ルートが一般的になりましたね。
ディプロマもらいました。



地球温暖化と言いつつ、最後の陸地を越えると極圏は、太陽こそ落ちませんでしたが、ほぼほぼ氷に囲まれていましたけれどね。
最近新聞見なくなりましたね。

ある意味シンプルなフィンランドらしい朝食。

スペインの壮麗なカトリック教会、特にバロック様式やゴシック様式で彩られた教会群を訪れると、ただの建築物というより、「信仰の力」と「文明の自負」の結晶であることが強く伝わってきます。
天井高くそびえるヴォールト、金箔をふんだんに用いた祭壇、聖人たちの殉教や奇跡を描いたフレスコ画――それらはすべて、「自らの信仰が普遍であり、世界の隅々にまで伝える価値がある」と信じて疑わなかった宣教師たちの精神の反映です。
特に16世紀から17世紀にかけてのスペインでは、「教会=王権と神の合一の象徴」でもありました。
教会の荘厳さは単なる宗教的熱意だけでなく、「我らこそ文明の担い手である」という帝国意識の表れでもあります。
そしてその信念を胸に、フランシスコ・ザビエルのような宣教師たちは、危険を顧みずにアジアやアメリカの未踏の地へと旅立ちました。
彼らにとって、異文化は恐れるべきものではなく、「救済すべき対象」であり、自らの使命は神から授けられたものでした。
「大聖堂(Catedral de Sevilla)」の中に足を踏み入れると、まるで天に向かって祈りが立ち昇っていくかのような高揚感があります。
あの空間の中に身を置くと、ザビエルらがなぜ命をかけて布教に出かけたのか、その心の在りようが少しだけ理解できるような気がします。
もちろんその宣教活動には、植民地主義や文化破壊といった負の側面もありました。
しかし、スペインの教会が今なお語りかけてくるのは、当時の人々が持っていた「真理への確信」と「世界に希望を届けたい」という純粋な衝動でもあります。
あの石と光の中には、文明の光と影、信仰と政治、救済と支配が複雑に織り込まれているのです。



「剣と十字架」の時代:西洋帝国主義と東洋の自衛戦略
16世紀から17世紀にかけて、世界は大きく動いていた。西洋では大航海時代を経てスペイン・ポルトガルの海洋帝国が隆盛を極め、一方の東洋では、明・清・ムガル・日本などの文明圏がそれぞれに独自の政治秩序を確立していた。
この時代の西洋世界を動かしていた大きな原動力の一つが、「カトリック世界の再構築」という宗教的野心である。16世紀初頭、ルターによる宗教改革によりヨーロッパはプロテスタントとカトリックに分裂。これに対抗する形で、カトリック教会はイエズス会(Jesuitas)を中心とした「反宗教改革(Counter-Reformation)」を展開した。
1540年にロヨラのイグナチオが創設したイエズス会は、単なる布教団体ではなかった。彼らは高度な教育を受け、言語習得に長け、知識・文化・医術・天文学までも活用して、布教とともに政治的影響力を浸透させる「知的征服者」でもあった。彼らの布教は、常にスペインやポルトガルといった海洋国家の交易・軍事・政治と一体化して進められていた。
一例として、フィリピンでは1565年のマニラ征服以降、イエズス会が先住民をキリスト教に改宗させ、スペイン王政の名の下に統治構造を組み替えた。南米でも、パラグアイの「イエズス会レドゥクシオン(集団村落)」が独自の自治共同体を築き、国家権力すら超える支配力を有していた。


では、なぜ同じような布教活動が日本では成功しなかったのか?
日本では、戦国時代の混乱の中で、キリスト教はむしろ有力大名にとって「一時的な武器」として迎え入れられた。1549年のフランシスコ・ザビエル来日以降、ポルトガルとの貿易や鉄砲の供給を受けるため、九州の大名たちは競って洗礼を受け、教会の建設を許可した。しかし、彼らはキリスト教を精神的信仰としてではなく、戦略的手段として位置づけていた。
この布教活動の拡大に対して、織田信長は当初は寛容だった。彼は仏教勢力との対立構造を背景に、カトリック勢力を相対化させることで国内の宗教勢力の均衡を図っていた。しかし、イエズス会が民衆の精神的帰依を深め、領主すら「神に従属させる」構図を取ることを見抜くと、一定の距離を置くようになる。
さらに豊臣秀吉は1587年、バテレン追放令を発布。これは単に宗教弾圧というよりも、イエズス会による過度な信者囲い込みと、日本人奴隷の海外輸出という不道徳な側面を問題視したものであった。
最も決定的だったのは徳川家康の判断である。1600年、漂着したイギリス人ウィリアム・アダムス(三浦按針)から、スペインやポルトガルが宣教師を前衛として布教→内政干渉→征服という段階を経てアジアや南米を支配している実情を聞き出すと、彼はキリスト教を「宗教的仮面をかぶった政治戦略」と見抜いた。
その結果が、1614年の全国禁教令である。この禁教令により、日本は「西洋型植民地主義」を唯一跳ね返した非キリスト教文明となった。以後、日本は幕末まで250年にわたり、外来宗教による国家転覆を防ぎ続けることになる。
この日本の選択は、当時の東洋においても特異であった。たとえばインドでは、ムガル帝国が内包的には宗教多様性を許容していたが、西洋勢力との抗争に敗れ、最終的にはイギリスに植民地化される。一方で中国は、初期はマテオ・リッチらの知的布教に好意的だったものの、やがて「典礼問題(Rites Controversy)」により布教を全面禁止し、欧州との断絶に至る。
西洋においては「神の名のもとに」拡張することが正義であり、イエズス会はその最先端であった。しかし日本の為政者たちは、その宗教の背後にある国家戦略を鋭く見抜き、自国民の精神的主権と政治的独立を守り抜いた。
信仰の名を借りた支配に抗した東洋のリアリズム——それが、家康と信長の決断の核心である。
フレンドリーな都市はスペインに多い。マラガは世界2番なのか。

思えば僕は、専門医を取って以降、自律神経、疼痛、麻酔、レーザー治療、レーザー工学、肥満治療、レーザーアシストのドラッグデリバリーなどなど、数多くの分野で国際学会での研究発表をしてきました。
その数25年間で400回以上。
自分としては同じ発表をするのが嫌で、新たな事を学び、好奇心で新たな分野の学会に参加して、ある程度身につけると他の分野に興味の対象を変えてきました。
学会発表が医師にとって重要である理由は、単なる「義務」や「形式」では語り尽くせません。
それは、臨床医としての実力や専門性を「見える化」し、医学界との対話のなかで自らの知見を深化させる行為でもあるからです。

以下、いくつかの視点からその意義を整理してみましょう。
1. 臨床知見の言語化と体系化
日々の診療で得られる経験は膨大ですが、それを第三者が評価可能なかたちでまとめることは容易ではありません。学会発表は、日常診療での「気づき」や「工夫」を、エビデンスと共に整理し、論理的に表現する場です。これは、医師自身の臨床思考を磨く最良の訓練でもあります。
2. 医療の進歩に貢献する責任
医師は「科学者としての倫理」も背負っています。患者の診療で得られた知見を個人の中に留めるのではなく、医学界全体に還元することが、科学の進歩につながるのです。特に希少疾患や新しい治療法などは、自身の症例報告が世界初の情報源になることもあります。
3. 同領域の専門医との対話とフィードバック
発表は一方通行ではなく、質疑応答を通して他の専門家の見解や批判を受けることができます。これは、自身の見解が「独善的」にならないための重要なプロセスであり、まさに医の哲学における“無知の知”に通じる姿勢です。
4. 医師としての信用とブランディング
学会発表歴は、専門医試験、大学・病院での昇進、研究費の獲得、医療機関の信頼度向上など、さまざまな場面で評価されます。特に自由診療や開業医の場合、エビデンスに基づく発信は、患者からの信頼に直結します。
5. 若手医師や学生への教育的意義
自身が学会発表する姿を見せることは、後進への教育にもなります。医師という職業が「学び続ける存在」であることを体現することで、医局・診療科の文化にも良い影響を与えるのです。
6. 国際学会と世界との接続
国内学会にとどまらず、国際学会で発表することで、世界の最新知見と接続されます。異なる医療文化・ガイドラインとの比較は、視野を広げるうえでも非常に有益です。
締めくくりに
学会発表とは「単なる報告」ではなく、医師が臨床・研究・教育の三位一体を実現するための修行の場とも言えます。そこで培われる「科学的態度」「社会との接点」「自己の限界を知る知性」こそが、良き医師の資質そのものなのかもしれません。
最近直美問題が盛んに取り上げられていますが、せっかく医師になったのに、アカデミックな分野から遠ざかってしまうのはあまりに惜しすぎる。医学はおそらく宇宙と並び、人間の好奇心を満たしてくれる最高の学問です。
どの分野を選んでも興味がどんどん湧いてきます。研究する場所をぜひ自分で見つけてもらいたいですね。正直なところお金を稼ぐよりも、遥かに楽しい事なんですけれどね。