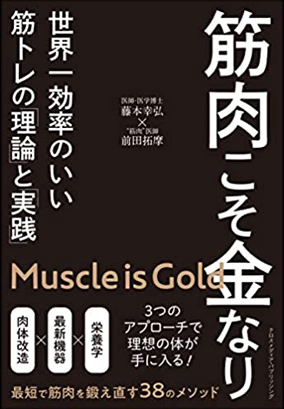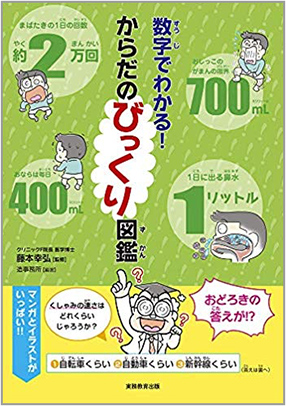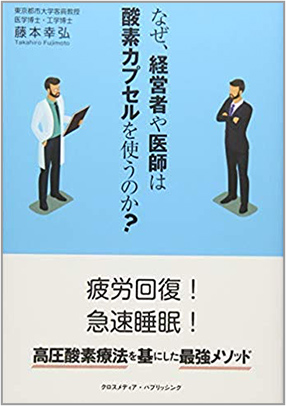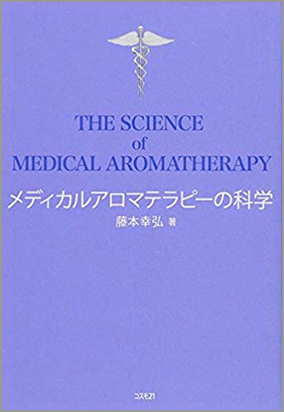今週末の抗加齢医学会で発表したNMNの講演の記者会見が、先程行われたのですが、早速記事になりました。
僕もYahoo!ニュースに再登場。名前だけですが。笑。

60歳いとうまい子、15年間続けている健康の秘訣は「1日1食」「パフォーマンス上がった」



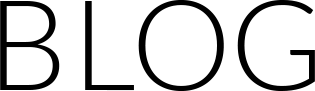 藤本幸弘オフィシャルブログ
藤本幸弘オフィシャルブログ

今週末の抗加齢医学会で発表したNMNの講演の記者会見が、先程行われたのですが、早速記事になりました。
僕もYahoo!ニュースに再登場。名前だけですが。笑。

60歳いとうまい子、15年間続けている健康の秘訣は「1日1食」「パフォーマンス上がった」


FBで過去の投稿が出てきました。
そういえば、前シーズンはまさに12月17日のシーズン初めの足骨折で全く滑れなかったなあ。
今年はニセコ行こう。
2020年12月27日

https://www.facebook.com/takahiro.fujimoto/videos/10225298848686670
科学者になるということ──博士号取得は“科学的思考”の訓練場である
「博士号って、ただ論文を書くだけで取れるんですか?」
僕はこれまでに医学・工学・薬科学・経営管理学と、4つの博士号を取得してきましたが、この質問は何度となく受けてきました。
確かに形式上は、テーマを決めて研究し、規定の本数の英文論文を書き、成果をまとめた学位論文を書き上げ、審査を通過すれば、博士号は得られます。
でも、本当の意味での博士号の価値は、その過程の中にあると僕は思っています。それは、知識の到達点ではなく、「思考する力を鍛える道のり」そのものなのです。

1|博士号は“科学的思考”を鍛える最良の道具
博士号を目指す過程で、あなたはこんなことを繰り返します。
・論文を読み、問いを立てる
・仮説を組み立て、検証する
・思い通りにいかないデータと向き合う
・それでもあきらめずに、言葉にする
これらはすべて、「どうして?」と問い続ける力、そして根拠をもって答える力を育ててくれるのです。
◉ たとえばこんな変化が起きてきます
• 世の中の情報に簡単に惑わされなくなる
• 専門外の分野でも本質を見抜く力がつく
• AI時代に必要な、“人間だからこそできる問い”が立てられる
それは、目に見えるものではないけれど、確かにあなたの中に根を張っていきます。
⸻
2|博士号は「その分野で、一番深く考えた人」であるという証
博士号とは、知識の量ではありません。
「このテーマに関して、世界で最も深く、誠実に考えた」
──その証が、Ph.D.という名前に刻まれるのです。
◉ たとえばこんな場所で活かされます
• 大学や研究機関での教育・研究職
• 企業のR&D部門や開発プロジェクト
• 臨床と基礎をつなぐ、橋渡しの専門家としての活躍
社会は、「問いを立ててきた人」を必要としているのです。
⸻
3|博士号は“信頼”という形で、あなたを支える
ビジネスの世界でも、博士号はじわじわと効いてきます。
すぐに役立つ資格ではないかもしれません。
けれど、相手の目には映るのです。
「この人は、自分の頭で考え続けてきた人なんだな」と。
◉ たとえばこんな場面で力になります
• 海外との技術交渉や共同研究
• 起業やベンチャー創業時の信用
• ディープテック投資家との対話
いま注目されている企業の多くの創業者は博士号を持っていました。
⸻
4|博士号は「人生の問い」にも、応えてくれる
博士号の最大の価値は、じつはもっと個人的なところにあるのかもしれません。
「自分の問いに、自分で答えを出す」
それって、なかなかできることじゃないんですよね。
けれど博士号を取るというのは、まさにそれをやり切ったという証。他人の評価じゃなく、自分の納得を追い求めた人の証です。
◉ たとえばこんな変化が生まれます
• 誰かの顔色ではなく、自分の判断で物事を決められる
• 世界を「仮説」として見る哲学的な目線が育つ
• 成果よりも「プロセス」に価値を見出せるようになる
これは、どんな資格や職歴にも代えがたい財産です。
⸻
5|博士号は“構え”であり、“姿勢”である
「博士号があるからすごい」のではありません。
「博士号を取る過程で、自分で問い、考え、書き、答えた」その構えと姿勢が、あなたを強くしてくれるのです。
⸻
◆ 査読──科学者が初めて世界と対話する場所
本や言ってみれば教科書は自分の考えを書くことができますが、論文はそうはいきません。初めて論文を出すとき、見知らぬ査読者から次々と問いが飛んできます。
「なぜこの方法なのか?」
「このデータで、その結論は本当に言えるのか?」
逃げたくなるような瞬間もあります。
でもそこで、自分の言葉で答えようとする過程にこそ、科学者としての始まりがあるのです。
⸻
◆ 「問いを立てる力」は、教科書では学べない
学部や修士までは、“与えられた問いに答える力”が評価されます。でも博士課程では、誰も問わなかったことを、自分で見つけることが求められます。
孤独でも、出口が見えなくても、それでも問い続ける。
その姿勢が、やがて“本物の知性”になるのです。
⸻
◆ 誰もが間違える。それでも進む、それが科学
アインシュタインですら、特殊相対性理論への宇宙定数の導入を「人生最大の過ち」と語りました。
だからこそ、博士課程で失敗したり、仮説が崩れたりすることは、むしろ当たり前。それにどう向き合うかが、科学者としての“品格”なのです。
⸻
◆ 博士号とは、称号ではなく「思考の型」
知識はAIに任せればいい時代。
でも、「問いの意味を問う力」、「根拠を吟味する力」は、訓練された人にしか育ちません。
博士号はその訓練を受けた人の証です。
⸻
小保方事件が教えてくれたこと
2014年、STAP細胞をめぐる騒動は、科学界に大きな教訓を残しました。Nature誌に掲載された論文は、のちに不正が明らかとなり撤回されました。
改ざんとつぎはぎだらけの画像。再現できないデータ。メモ書き程度のノート。世界の科学者がしのぎを削る再生医療の世界で、デッサンレベルの研究論文を発表してしまった事件。後にこの分野で米国が特許を取りましたから、理論は正しかったかもしれませんが、エビデンスが全く足りなかった。彼女を擁護する一般人の声もありますが、科学者の目から見ると、共同著者の自殺まで引き起こした日本の科学の信用を大きく傷つけた事件でした。
「思考の構造」が整っていなければ、注目は時に破滅へと向かう。博士号とは、まさにそれを防ぐ“最後の壁”でもあるのです。
⸻
ただし──神様は、越えられない壁は与えない
今あなたが直面している壁――それが査読かもしれないし、データの迷路かもしれない。
でも、ひとつだけ信じてほしい。
それを越えられる力が、あなたにはきっとある。
博士号を取るというのは、
一つの論文が通ることではなく、
“自分で問い、自分で考え、自分で語る”人間になること。
⸻
結びにかえて
科学者としての旅は、誰かが正解をくれるものではありません。指導教官がいなくても、孤独なときもあるかもしれない。でも、論理と思考という道具だけは、いつもあなたの手の中にある。
だから、恐れずに問い続けてください。
書いてください。答えてください。
科学者の出発点は、いつだって「一人で書き、一人で答える」ときに始まるのです。
【北鎌倉・作陶ワークショップ開催のお知らせ】
──魯山人の登り窯を継ぐ河村喜史先生とともに──
来る 6月22日(日)、北鎌倉の陶芸家・河村喜史先生による特別な作陶体験会を開催いたします。
かつて魯山人が登り窯を構えたその土地で、現代に受け継がれる「手から生まれる美」の時間を、皆様と共有したく存じます。
◆時間:13時〜/16時〜 の2枠(各回定員制)
◆ゴルフ医科学研究所(営団地下鉄 半蔵門駅 麹町駅)
◆参加費:20,000円(税込)
◆作品数:最大2作品まで制作可
◆初心者歓迎・手ぶら参加OK
⸻
【土から器へ──“ゼロイチ”の喜び】
私自身、コロナ禍をきっかけに作陶を始め、はや5年が経ちました。これまでに60を超える器を手がけてきましたが、粘土という“無”から、“器”というかたちを創造する行為は、まさにゼロからイチを生み出す快感そのものです。
火を入れられる前のやわらかな土を、手で触り、形にしていく工程は、日常の中では得がたいアーシング効果(Earthing)ももたらします。現代人の多くが忘れてしまった「大地とつながる感覚」。それを思い出させてくれる静かな時間が、ここにはあります。
⸻
【ご参加をお待ちしております】
土に触れ、無心になり、形を作るという営みは、どこか瞑想にも似ています。自分自身と向き合う豊かなひとときを体験してみませんか?ご希望の方はメッセいただくか、こちらにコメントくださいね。




生殖医療とゲノム医療の交差点──「命の選別」をめぐる現在と、かつての日本社会の記憶
今月号の日本医師会雑誌。
いつもより薄かったのですが、色々考えさせられる内容でした。
ゲノム医療の進歩が、生殖医療の在り方を大きく変えようとしています。
体外受精や出生前検査の現場では、胎児や胚のゲノム情報をもとにした判断が、すでに現実のものとなっています。
たとえば、非侵襲的な方法で染色体異常の有無を調べるNIPT(新型出生前検査)や、体外受精の段階で遺伝的異常を調べるPGT(着床前遺伝学的検査)などが代表的です。
中でもPGT-Mは、特定の遺伝子変異によって発症する重篤な疾患を回避する目的で行われ、いわば「遺伝病を次世代に残さない」という明確な意図を持って導入されています。
こうした技術は、確かに家族にとって大きな安心や選択の幅をもたらしてくれるものです。
しかし同時に、それは「命の選別」とも受け取られかねない問いを社会に突きつけています。
「この命は生きる価値があるのか」という問いを、私たちはどこまで見つめる準備ができているでしょうか。
■ かつての日本には、障害をともに受け入れる社会的土壌があった
振り返ってみれば、かつての日本社会には、障害や特性のある子どもを「特別視」せず、生活共同体の中に自然に迎え入れる文化的な懐の深さがありました。
江戸時代の盲人たちは、「検校」や「座頭」として鍼灸や音楽の分野で尊敬され、職能集団として自立した暮らしを営んでいました。また、村社会では身体や知的な違いがあっても、できる仕事を分担し合うことが「当たり前」であり、能力によって人間の価値が決まるという思想はそれほど強くありませんでした。
民俗学者・柳田國男が記したように、異なる者へのまなざしは時に神聖性と結びつき、「おかしみ」=神の気配とすら捉えられていたのです。
仏教や神道の影響も大きかったでしょう。「どの命も、かけがえのないもの」「障害もまた因縁のひとつ」と捉える思想は、科学的説明よりも先に、人間の存在をそのまま受け入れるまなざしを形づくっていました。
■ ゲノム医療の時代に、私たちは何を取り戻すべきか
もちろん、現代医療の恩恵を否定するつもりはありません。ゲノム医療は、病気を未然に防ぎ、遺伝性疾患による苦痛から家族を守る力をもっています。
しかし、その技術が突きつける「選択の自由」は、ときに過剰な責任と孤立を親に課すこともあります。
「産むか、産まないか」「知るべきか、知らぬままでいるべきか」。その決断の裏には、倫理や哲学、そして文化の支えがなければなりません。
もし私たちが、障害をもつ子どもをあらかじめ排除する方向にのみ進むとすれば、かつてこの国にあった「ともに生きる知恵」は、いつしか静かに消えていくでしょう。
■ 終わりに──技術とともに、「まなざし」も未来へ
ゲノム医療の進歩は、未来の家族像を塗り替える力を持っています。しかしそれは同時に、私たちがどんな社会を望むのか、どんな命を迎え入れるのかという倫理的な問いにも、正面から向き合うことを求めています。
かつての日本にあった「すべての命を丸ごと受け止める力」。それを忘れずに、現代医療とどう折り合いをつけていくか。
私たち一人ひとりが、その問いを他人事にせず、自らに引き寄せて考えるときに来ているのかもしれません。