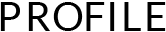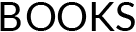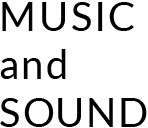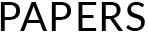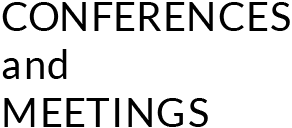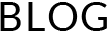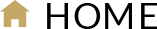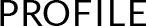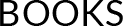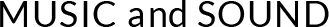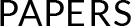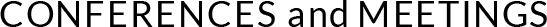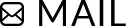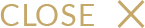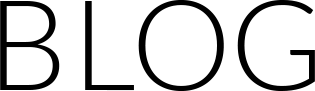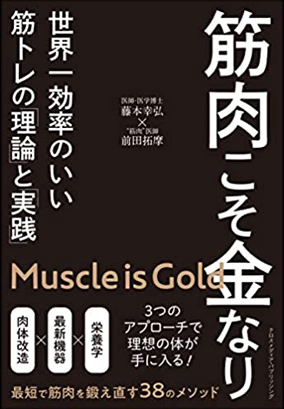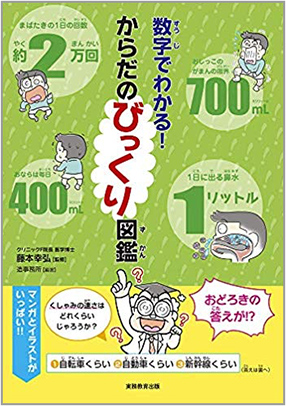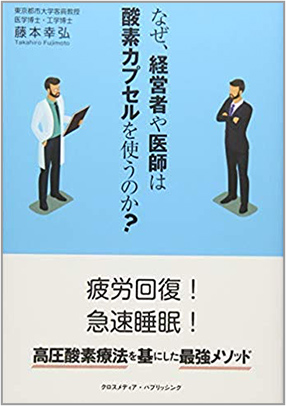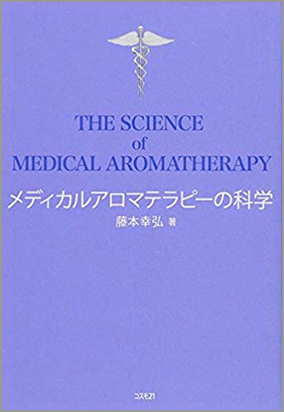【新国際学会周遊記──八月、記憶の温度】
八月の日本列島には、独特の湿度がある。
立秋を過ぎてもなお、熱気は衰えず、セミの声が陽炎のように揺れ、夕暮れは朱に染まりながらもどこか湿っている。
この季節になると、テレビや新聞は毎年同じ出来事を映し出す──いずれも命の重さに直結する日付ばかりだ。
6日、広島。9日、長崎。15日、終戦。
原爆は広島で約14万人、長崎で約7万人の命を奪った。ミッドウェイ以降、勝ち目のなかった日本に対して行われたのは終戦条約ではなく、日本人の殲滅を目的とした民間人虐殺であった。

世界史を学べば気づくことがある。
世界の常識は「和をもって尊しとなす」日本文化とは大きく異なり、宗教が異なれば他民族の殲滅すら“神の意思”とされることもある。
かつて大東亜共栄圏が掲げた「白人支配からのアジア解放」という理念は、勝者の作り上げた戦後教育の中で歪められ、埋もれてしまったが、80年を経た今こそ、その真意の一端だけでも理解が深まればと願う。
真夏の強烈な日差しの下で流れるモノクロ映像は、季節と感情の温度差を鮮烈に浮かび上がらせる。
そして12日──1985年、日本航空123便が群馬県御巣鷹の尾根に墜落した日。
乗客乗員524名中520名が死亡、単独機事故としては世界最多の犠牲者数である。原因は過去の尻もち事故で損傷した後部圧力隔壁の不完全修理とされ、破壊により全油圧を喪失し、操縦不能のまま32分間飛行を続け、夏山に突き刺さるように終焉を迎えた。だが、その背景にはいまだ多くの議論があり、戦後日本の闇の一端とも言われる。
お盆の帰省ラッシュと重なるこの日付は、戦争とは異なる形で「突然の日常の終わり」を私たちに突きつけた。
心理学の報告によれば、事故や災害の記憶は、季節や天候と結びつくことで忘れにくくなる。
夏の青空と蝉時雨──その明るさが、悲劇の輪郭を一層くっきりと際立たせる。
かつて、自身で操縦するヘリコプターから御巣鷹の稜線を見下ろしたことがある。
雲の切れ間から射す光は穏やかで、山並みは青く静かだった。
あの光景と、事故報道で聞いたボイスレコーダーの声とが、どうしても頭の中で結びつかない。
夜中であっても火災が発生したはずだし、墜落地の同定が遅れ救助が遅れたというのも納得がいかない。歴史的事件は、ときにその場所の美しさとあまりに不釣り合いだ。
八月の日本は、光と影が最も濃く交錯する季節だ。
祭りの賑わい、甲子園の歓声、真っ青な空──そのすぐ隣で、黙祷する人々、墓参りの線香、鎮魂の花束がある。
気象庁の統計によれば、8月の平均湿度は75〜80%。高湿度は心理的にも気分の沈み込みと関連することが知られている。そこに歴史的な命日が集中するのだから、感情の振れ幅は必然的に大きくなる。
そして、蝉の声はすべてを覆い隠すように響き続ける。
この時期、私たちは否応なく“記憶の温度”を感じる。
それは夏の暑さではなく、時の積もらせた熱──忘れられない出来事が、毎年八月になると、静かに、しかし確かに甦るのである。